077:欠けた左手
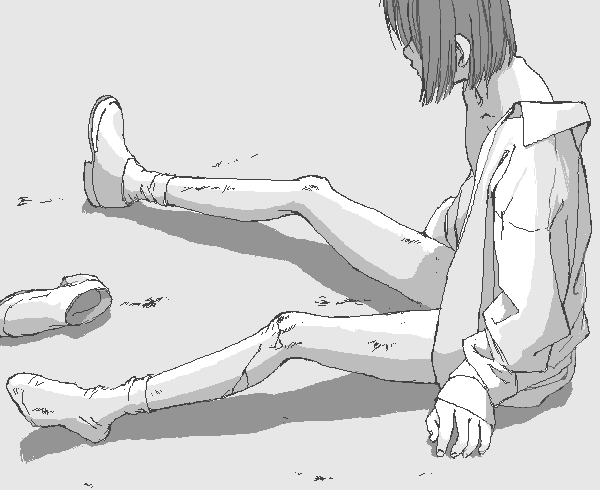
※こちらはsoftcell73の猫目さんちで頂戴した「強姦直後アキラ」
この、お人形みたいな体勢と靴下が堪りませんでしょう!ショタ心をくすぐられます。
これは是非文をくっつけさせて頂きたいと思ったのですが、微妙な出来。
一応こちらが起点、という感じで・・・。
猫目さん、萌えイラ本当にありがとうございました!幸せですv
一度されてしまうとそういう匂いがついてしまうのか、それとも元々僕の性分なのか。
指導碁の客やその秘書に、体を買われるようになってからしばらく経つ。
さすがに同業者とはないが、知られるのも時間の問題かも知れない。
実際自分の専属(愛人という事だろう)にならなければバラすなどと脅しを仄めかしてきた
信楽焼の狸(と内心呼んでいるどこかの取締役)もいた。
知るものか。
大体、金に困って体を売っている訳ではない。
最初は単なる暴力だった。
次は既に客で、僕は暴力に負けたくないというだけの理由で抵抗しなかったし、
同じ理由で、ベッドサイドに置かれた金を丁寧に集めて受け取った。
金を取らなければ、僕は強姦された女性のように泣き寝入りするしかない。
金を受け取ればそれは「取引」という事になり、負けた事にはならない。
少なくとも引き分けだと自分で思える。
惨めな思いが、少しだけマシになる。
客同士にそれ程繋がりがあるとは思えないので、噂が流れた訳ではあるまいが
それでも時期を同じくして沢山の男が群がってくるようになった。
腹の突き出た金持ち。
毛深い男。
しなびた老人。
色男気取りの若い男。
僕は等しく相手をした。
男である僕を抱くということは元々そういう趣味なのだろうか、
世間には存外潜在的同性愛者が多いものだなどと他人事のように思いながら。
そんなある日、緒方さんにマンションに来ないかと誘われた。
一通り碁の関係の話をした後、会話が途切れる。
断りもなく煙草に火を点けた緒方さんは、窓の方を向いて細く長く煙を吐いた。
これは何か重要な話、或いは言いづらい話がある時の前触れだ。
「最近・・・。」
言いかけてから目を細めてもう一度煙を吸う。
珍しい。
「・・・君がきれいになったと噂する連中がある。」
「きれい、ですか。」
「ああ。」
「自分では分かりませんが、もしそのような事があったとしても適切な表現ではないと思います。
僕は男ですし。」
「ではなんと言えばいい。」
「さぁ・・・。」
男ぶりが上がったのならそれなりの表現があるだろうと思ったが言わなかった。
自分で言える筈もない。緒方さんも人が悪い。
「『色気が出てきた』、とでも?」
「それも。」
「ああ。多分正鵠ではないな。『魅力的になった』、でも間違いではないのだが。」
段々と苛立ってくる。
こういう回りくどい物の言い方は緒方さんの悪い癖だ。
そういうのは女性を口説くときにでもやってほしい。
緒方さんなら、本当はとっくに一番適切な表現を用意している筈なのだ。
僕はそんな当て物に付き合っている程暇ではない。
「さっきから、何が仰りたいんですか。」
「怖い顔をするな。」
「言いたいことをさっさと言ってくれないからです。時間の無駄です。」
「ああ・・・。」
目を伏せて、もう一度煙を吸う。
もしかして・・・焦らして遊んでいる訳ではなくて、本当に言いづらいことなのだろうか。
だが、今度はふっ、と短く一気に吐き出すと、意を決したようにあっさりと口を開いた。
「顔に、『ファック・ミー』と書いてあるぞ。」
・・・・・・。
「一見何も変わらないようだが、以前のおまえには無かった隙だらけだ。
押し倒してくれと言わんばかりだ。無論それでも棋士でそんな勇気のある奴はそうそういまいが、」
「・・・・・・。」
「元々金でオレ達を買っている連中の中には、そうでないのも、いるんじゃないか?」
「・・・・・・。」
「というのを心配したわけだ。」
・・・一度。
たった一度許してしまっただけで、男に体を開いてしまっただけで、
そんなに無防備な顔になっていたのだろうか僕は。
ならば、最初からそのような性分なのかも知れない。
でなければ恐ろしく甘くて脆い、砂糖菓子のような精神の鎧だったのだろう。
そんなものは粉々に壊れてしまえばいい。
僕は、笑った。
出来るだけ惨めったらしく見えないように。
「・・・ファック・ミー。」
緒方さんは痛みに耐えるように眉を寄せて固く瞼を閉じた。
目を開けた時には無表情に戻っていて、僕の腕を掴むと寝室のドアを蹴り開けた。
「上手いもんだ。」
両手と口で奉仕した僕を、緒方さんが冷たく褒める。
いつもより少しだけサービスしたよ。知らない人じゃないからね。
左手で緒方さんのものを扱きながら、右手をベッドサイドテーブルに伸ばす。
鞄から出して置いたジェルのチューブを掴み、歯で蓋を外す。
「誰だ?」
「何がですか。」
「最初におまえにこんな事を教えた奴だ。」
そんな事アンタに関係ないだろう!
なんて思っても言わない。アイツじゃないんだから。
「取るに足らない男ですよ。」
「ふ・・・ん。」
「・・・・・・。」
どうだろう。分かっただろうか。
いや、よく考えれば緒方さんならきっと見当がついているのだろう。
だとすれば、「取るに足らない男」だなどと不用意に言ってしまったせいで、
逆に意識しすぎる程している事が露わになってしまった。
クソッ!
どうしよう。
黙っているのは子どもっぽいと思ったが、僕には本当の事を言う勇気も、嘘を吐く自信もない。
だから何も言わず口にチューブをくわえ、ひり出した潤滑剤をたっぷり手につけて
自分の後ろに回した。
「あ・・・っ。」
自分の指で広げるだけで、ぞくりとした震えが体の中心を走る。
自分が勃ち上がり、先から透明な液がとろりと流れ出しているのが分かる。
これから起こる事への期待。
中に埋め込まれる楔の形を確かめるように、人差し指だけを使ってゆっくりと撫で、
もう一度舌で濡らした。
「ね・・・もう・・・。」
「どうして欲しい。」
男達はみんなこうだ。
僕の体だけでなく、心まで征服したがる。
自分の思うとおりのセリフを言わせたがり、僕の方から自分を求めているのだと思いたがる。
別に構わない。
欲しいものを、与えてあげるよ。
手の動きを早めて、唇でくわえ込むようにする。
「分かってる、くせに・・・。」
中年の男が喜びそうな、卑猥な言葉をいかにも恥ずかしげに言うと、緒方さんは
僕の手を外して指を絡め、のし掛かってきたので、尻の指も抜いてティッシュで
不器用に拭った。
「痛い・・・。」
乱暴に扱われるのには慣れているが、黙って耐えているとエスカレートして来ることを
経験上知っているので、早めに音を上げる。
そう、彼等は僕が弱音を吐くのを待っているのだ。
「おが、た、さ・・・。」
腰を突き出して、ねだる。
もう一度口で「入れて下さい」なんて言うのは、もう少し後だ。
焦らされるのが好きな訳じゃないが、彼等の中にはそうする事に無上の喜びを感じる輩もいる。
だが緒方さんはそういうタイプではなかったらしく、舌を突き出して挑発しただけで
絡めた指が更に強く撓められ・・・。
・・・・・・?
っ!!
「・・・!おが、」
ぱき。
・・・・・・本当に、
「枯れ枝を布でくるんで折ったような」音がするんだ。
そのままじゃないか。
「・・・・・・!」
ていうか、痛・・・。
「・・・おまえの指は、こんな事をするためにあるんじゃない。」
「・・・・・・。」
「碁石を持つ為だけにあるんだ。
おまえの体はおまえだけのものじゃない。日本の囲碁界の宝なのだという事を分かれ。」
「・・・だからって、」
「だから左手にしただろう。」
離された左手を持ち上げてみたが、手首から真ん中にかけてはまだ痺れている。
折られた中指は人形の壊れたパーツのようにぶらりとしていて、自分のものでないようだが
少し動くだけで一瞬息が止まる程の痛みが走った。
僕の股間も当然ぶらりとしていて、額からは汗が噴き出す。
「分かったら、二度とこんな事はするんじゃない。」
「・・・分かり・・・ましたから、病院へ・・・。」
突然起こった事故、いや事件に、頭の回転が全く止まった。
ただ手を治さなければ、痛みを止めなければ、という動物並の思考だけが生き残り、
怠惰な世界は埃を掃いたようにかき消えた。
駆け引き位しか楽しみのなかった先程までの時間が、如何に贅沢な退屈であったかと
左手がひっきりなしに訴えてくる。
緒方さんは手早く体を拭って服を身につけると、僕の体も拭いた。
尻の穴にもティッシュでくるんだ指を入れられたが、既に何も感じなかった。
「ああ、それと。」
ちゃり、と鳴る車のキー。
「進藤にもその指を見せて、その内おまえのも折りに行くと伝えて置け。」
「・・・・・・。」
「勿論右手だ。」
・・・恐ろしいような、嬉しいような、気持ちイイような、苛立つような。
複雑すぎる感情に、僕はいかなる表情も浮かべることが出来なかった。
−了−
※緒方さんの躾道。体罰派?
猫目さんのイラを起点にさせて頂いたんですが、ホントは左手のぶらんとした感じを
是非生かしたかったんですよね。やや心残り。
